教養教育院紹介
教養教育院の使命と役割
| 東北大学は、2008(平成20)年に教養教育院を発足させました。これは、学部および大学院の教育・研究の経験を積んだシニア教授が改めて全学教育に携わることで、広範かつ高度な教養教育を実施するためのものです。さらに、2010(平成22)年度からは全学から選ばれた教養教育に強い情熱と優れた教育能力をもつ数名の教員の兼務が始まり、より一層広い視野から教養教育の充実を図ることになりました。2018(平成30)年4月に就任した大野総長は、「最先端の創造、大変革への挑戦」を目標に掲げ、東北大学が取り組むべき挑戦を「東北大学ビジョン2030」にまとめました。教育面では、「大変革時代の社会を世界的視野で力強く先導するリーダーの育成」が掲げられています。現代の多様で複雑化した諸課題に挑むリーダーには、豊かな教養と深い専門性に基づく確かな判断力が求められます。大学での教養教育には、多様なものの見方に触れ、統合知のあり方を学ぶ機会を提供するという重要な役割があります。それ故、何を、いつ、どう教えるかを常に問い続けていかなければなりません。教養教育院は、様々な創意工夫によって初年次学生の学びへのモチベーションを高める授業を創り出し、さらに、高年次学生や大学院生への教養教育の充実のために先導的な役割を果たします。 | 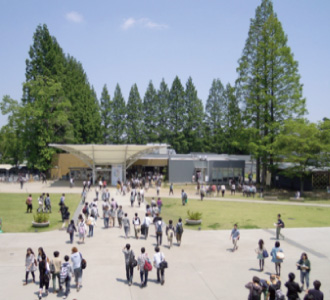 |
教養教育院の構成
| 教養教育院は総長特命教授と教養教育特任教員から構成されています。両者の任務は以下のとおりです。総長特命教授 本学を定年で退職した教授の中から、すぐれた教育研究業績があり、かつ教養教育にふさわしい優れた教育能力をもつ教員として総長が任命します。幅広い知識と独創的な研究経験を活かし、学問・研究の魅力と醍醐味を学生に直接語ることによって、一人一人の学生を学びと研究の世界に誘います。教養教育特任教員 教養教育に強い情熱と優れた教育能力をもつ教員の中から、教養教育院兼務で全学教育科目を担当する教員として総長が直接任命します。さまざまな創意工夫によって教養教育を活性化することが主な任務です。 |
教養教育院設立の経緯
| 2007(平成19)年3月の「井上プラン2007」の中で、教育面については、①大学教育の根幹となる教養教育の充実、②知を創造できる専門教育・大学院教育の充実、③新たな教育システムの開発、④学生支援体制の充実、⑤意欲的な学生が受験する入試戦略の展開の5項目が掲げられました。これらを具体的に遂行するための手段の一つとして2008(平成20)年度に、幅広い知識と深い研究経験のある退職教授を総長特命教授(教養教育)として配置し、研究中心大学として、初年次ばかりでなく大学院生も対象として教養教育を担う「教養教育院」が新設されました。さらに2010(平成22)年度に、教養教育担当教員のうち教養教育院を兼務する教養教育特任教員の制度が始まりました。 |
主な活動・取組
| (1) 教養教育の実施 学部・大学院における教育研究の豊かな経験を積んだ総長特命教授が、その経歴にふさわしい内容と質の教養教育を実施します。全学教育科目にあっては、初年次教育だけでなく、いわゆる高年次教養教育科目の担当を通じて、学部専門教育科目との両輪となるような貢献も目指します。また、大学院教育にあっては、高度教養教育として大学院共通科目を担当しています。以上の具体的な担当科目やその内容については、総長特命教授の専門性または教養教育院に期待される事項を勘案して調整しています。《最近の担当科目例》
|
 |
| (2) 教養教育の推進 知的成熟と人間的成熟を目指す教養教育の重要性に気付きを与え、学部や大学院に在学の期間だけでなく、生涯を通じて自ら学び続ける人となるための強い動機を形成する活動を行っています。 |
|
| 《具体的な活動内容》 | |
| ・「教養教育特別セミナー」(全学部1年次全学生対象)の開催 【行事・イベントページに掲載】 学問分野を横断する重要な課題をテーマに据え、各分野の専門家からの講演と学生との直接討論により、課題の解決に向けた教養の重要性を自覚する機会を提供しています。 |
|
| ・「ILASコロキウム」(総長特命教授合同講義)の開催 【行事・イベントページに掲載】 主に本学若手教員の研究への取り組みを紹介し、専門性を高めるための基盤となる教養の役割を自覚する機会を提供しています。 |
|
| ・『教養教育院叢書』の出版 【刊行物ページに掲載】 主に教養教育特別セミナーやILASコロキウムで取り上げたテーマについて、より深く掘り下げた考察や新たな切り口の論考をシリーズ化した論文集として出版しています。 |
|
| ・『読書の年輪 ~ 研究と講義への案内』の刊行(毎年度) 【刊行物ページに掲載】 初年次学生が大学での学びを始める上で、一つの手引きと位置づけています。教養教育院教員が自らの教育・研究活動の経験を基に、一人数点の図書を紹介しています。 |
|
| ・東北大学学務審議会への参画 全学教育全般、学部専門教育や大学院教育で部局を横断する事項、学位制度などを所掌する学務審議会の構成員として、大学全体の教養教育の企画運営に参画しています。 |
|

